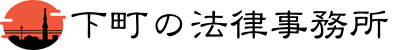平治の乱で捕らえられ伊豆に流されていた源頼朝は、以仁王の平家打倒の令旨を受け、治承4年(1180年)8月17日、挙兵しました。しかし、この挙兵は失敗。石橋山の戦いで敗退します。そのときの洞窟に隠れる頼朝主従を描いた前田青邨の「洞窟の頼朝」(重要文化財)を目にしたことのある方は、多い筈です。
<洞窟の頼朝>
鎌倉幕府成立の出発点になる頼朝の挙兵を、京都の貴族たちはどう見ていたのでしょうか?右大臣九条兼実は、その日記「玉葉」9月3日の条で、「伝え聞く、謀反の賊義朝の子、年来配所の伊豆国に在り。しかるに近日、凶悪を事とし・・・およそ伊豆・駿河国を押領し終わんぬ。・・・彼の義朝の子、大略謀叛を企つるか。あたかも将門のごとし。」と記しています。
右大臣九条兼実は、頼朝挙兵の1年後から長きにわたって頼朝と朝廷との交渉を取り次ぐことになる重要な人物です。このような人物ですら、頼朝の名さえきちんと認識せず、平治の乱の謀反人の子が将門の乱のような反乱を起こした程度の認識しか持っていませんでした。
吾妻鏡によれば、頼朝は挙兵失敗後、伊豆半島真鶴崎から渡海して船で安房国に逃れ、同年8月29日、敗軍の将として、猟島(現在の鋸南町竜島)に上陸しました。
猟島までは内房線安房勝山駅から徒歩10分位で行くことができます。
上陸地と目されている海岸は、サーファーや釣り人に人気のスポットになっている場所のようです。落ち武者の心象風景を象徴するかのように岩礁が所々に顔を出しています。その一角に、源頼朝上陸地点との石碑が建てられています。案内板には「ここで先着の北条時政、三浦義澄らと合流し、再起を図りました。」とあります。
猟島からは、東京湾を隔てて、遠く富士山を抱く三浦半島が望めます。
<猟島海岸> <頼朝上陸地点の石碑>
<富士山と三浦半島を望む>
上陸後、頼朝は、乳兄弟であった安房の豪族安西景益の平松城に身を寄せました。房総半島を北上する頼朝の行動の成否は、当面この地域を代表する大武士団で在庁官人の地位にあった上総国の上総広常と下総国の千葉常胤の去就にかかっていましたので、9月4日、頼朝は、上総広常に和田義盛を、千葉常胤に安達盛長を使者として送り、平家打倒の戦いへの参加を求めました。9月8日には千葉常胤から帰順の知らせが届きましたが、房総で最大勢力を誇る上総広常からは、千葉常胤と相談をしてからとの回答があるだけで一向に帰順の知らせが届きません。この辺のエピソードは、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で描かれましたので、ご覧になった方も多いはずです。
頼朝は、このような不安を抱えながらも、猟島上陸からわずか40日余りで鎌倉まで攻め上ってしまいます。敗軍の将が何故これほど短期間に快進撃ができたのでしょうか?この不思議の原因を探ります。
はじめに見ておくべきは、当時の日本の政治情勢です。
平安末期、膨大な荘園群と多くの知行国の領有及び日宋貿易からの利潤がもたらす経済力、そして全国規模で組織化された武士団の武力に支えられた平家の権力と後白河法皇の院政は、安定した政治秩序を作り出していました。
しかし、平治の乱(1159年)終結後に始まるあまりにも急速な平清盛とその一門の台頭ぶりは、長い間、自らに従属する存在として見下してきた摂関家をはじめとする伝統的貴族たちの反感を買うのに十分でした(源頼朝と鎌倉幕府:上杉和彦著)。
治承元年(1177年)、東山の鹿ケ谷で後白河法皇の近臣藤原成親、西光、僧俊寛らが平家打倒の密儀を行うという事件が発覚しました。
この事実を知った平家の対応は、実に厳しいものでした。
清盛は、治承3年(1179年)、今や反平氏の中心になった後白河法皇を幽閉して院政を停止させ、これを境に朝廷の政治の専権を握りました。清盛の治承3年のクーデターです。
<平清盛像(六波羅密寺像)> <後白河法皇座像(長講堂蔵)>
このような政治情勢下、後白河法皇の第二皇子以仁王は、治承4年(1180年)4月9日、源頼政と共に平氏打倒の兵を挙げ、諸国の武士や大寺院に宛てて挙兵への呼応を命ずる令旨を発しました。しかし、以仁王らは余りに準備不足でしたので、同年5月26日に宇治川の戦いで早々に討ち死にしてしまいます。頼朝の挙兵も、平家と伝統的貴族との対立に巻き込まれて心ならずも行ったものでしたので、東国の豪族(在庁官人)たちに対して事前に十分な政治工作を行う時間的余裕もなく,敢え無く失敗となってしまいました。
次に見ておくべきは、頼朝と安房、上総、下総の国々の豪族との関りです。
頼朝の安房への渡海は、単に落ち延びただけではなく、当初より計画されていたと見た方が良いように思われます(中世成立期の安房国―源頼朝上陸の背景―:野口実著)、との見解があります。
時の安房の知行国主で長く伊豆を知行していた吉田経房は、後白河法皇の近臣であっただけでなく、頼朝が少年時代に皇后宮などに伺候し ていた際の上司であり、北条時政とも関係がありました。同人が、頼朝や北条時政と意思疎通をしながら安房上陸を容認していた可能性があります。
また、平安末期、東国は桓武平氏の支配下に収められていましたが、中世の武士の家人には、隷属度の強いものと双務契約的性格を持つ隷属度の弱いものの二つがあり、東国の平氏家人は、家礼(けらい)型家人と称された後者のタイプが多かったと言われています(源頼朝と鎌倉幕府:上杉和彦著)。
しかも、東国の平氏家人には、源義朝によって組織された経験を持つ武士団が多く、三浦義澄、千葉常胤、上総広常、葛西清重らは、いずれもそのような平氏家人でした。
頼朝の猟島上陸は、敗戦の結果落ち延びたという側面があったものの、このような安房、上総、下総の国々の武士団の源氏との繋がりをふまえた上でのそれなりの成算を持っての行動だったのです。
三番目に見ておくべきは、清盛と平家の家人との関係です。
清盛が政治の専権を掌握したとはいえ、平氏の家人に対する支配体制には、大きな綻びが生じていました。
平家が当時の地方武士たちが直面していた在地勢力同士や一族間で生じていた紛争を、対立する一方を引級し、それを従属度の強い家人に組織するという方策によって解決しようとしたため、かえって在地社会が不安定化する状況が見られた(中世成立期の安房国―源頼朝上陸の背景―:野口実著)との指摘があります。
平氏が家人間の紛争を公平に裁くのではなくて依怙贔屓によって解決しようとしたため、平氏の家人間の紛争が多発して、それらが解決しないままくすぶっていたというのです。
頼朝は、このような状況の中で、敗軍の将として猟島に上陸したのです。上陸に際しては、ともに上陸した三浦氏の力を最大限に利用しました。三浦氏は、三浦半島から浦賀水道の制海権を掌握しており、安房国西部にも勢力を伸ばしていました。安房国の地理にも詳しく、上陸間もない9月3日、安房国の案内者(あないしゃ)として頼朝の再起へ向けて尽力したのです。頼朝襲撃を企てた長狭経伴も撃退しています。
もっとも、この撃退劇、三浦義澄が長年勢力争いをしていた長狭氏を頼朝挙兵に乗じて抗争に片をつけようとしただけだ、との指摘もあります。
三浦義澄以外にも、千葉常胤は下総の藤原親政と所領を巡って長く対立を続け、上総広常は藤原忠清と上総の支配権をめぐって対立関係に入っているといった具合で、平家の家人たちは家人同士であちこち紛争を抱えていたのです。
頼朝は、このような平氏の家人間の紛争を巧みに利用して、上総国の上総広常や下総国の千葉常胤らへの帰順工作を進めていったのです。
<千葉常胤銅像(千葉猪鼻城址)> <上総広常(歌川芳虎画)>
頼朝に呼びかけられた彼らは、新たな関東の覇者への道を歩み始めた頼朝の軍勢に加わって当面の対立勢力を打倒する道を選択し、頼朝は、平氏家人同士の対立を煽るようにして安房から北上して勢力を伸ばそうとしていきました。
頼朝の成功の最大の要因は、清盛の平家の家人に対する支配体制の綻びに、巧みにくさびを打ち込んで行ったことにあったのです。
ここで、少し脱線させてください。三浦氏が安房国西部へ勢力を伸ばしていたと言いましたが、三浦半島と房総半島の間には広大な東京湾が存在しています。猟島から富士山を望んだ写真でも分かるとおり、両半島の間には相当な距離があります。850年近くも昔に三浦氏が、この広い東京湾を隔てた安房国まで勢力を伸ばせたのか素朴な疑問を抱きました。
こうなったら、実際に海を渡ってみるしかありません。
猟島のある安房勝山駅から2駅の浜金谷駅そばの浜金谷港から、三浦半島の久里浜港までフェリーに乗船しました。
ゆったりと進むフェリーの後部デッキに座って、カンカン照りの日差しの中で、離れていく鋸山を中心とする低い連山をぼんやりと眺めていると、僅か40分で東京湾を横断してしまいました。
こんなに近いならば、当時安房国には有力な豪族が存在していなかったのだから、三浦氏の安房国西部への勢力伸長は十分あり得ると納得しました。
<浜金谷港出港> <フェリーより猟島を望む>
左の写真の浜金谷港の背後の山が標高329mの日本百低山に選ばれている鋸山、右の写真の鋸山の右側に続く低い丘が猟島付近です。
つづく
つづく